人生勝ち組になる秘訣:為末大はなぜ世界陸上で二つもメダルを獲得できたのか?
為末大選手といえば、2001年の世界陸上エドモントン大会で、オリンピック、世界陸上を通じて日本人男性として初めて陸上競技のトラック種目でメダルを獲得した選手です。
その後、2003年の世界陸上で末次選手が200mで銅メダル。
2005年のヘルシンキ大会で為末選手が再度400mハードルで銅メダルを獲得した以外は、日本人選手が個人のトラック種目でメダルを獲得したことは未だかつてありません。
つまり、オリンピックと世界陸上のトラック個人種目で日本人がメダルを獲得したのは3回しかなく、そのうちの2回は為末選手が獲得しているのです。
なぜ、為末選手は世界大会で2度もメダルを獲得することができたのでしょうか?
その秘訣を彼自身の著書『日本人の足を速くする (新潮新書 213)』から探ってみたいと思います。
彼の考え方はアスリートに限らず、わたしたちのような一般庶民の人生を良好なものにするためにも大変役に立ちます。
ぜひ、最後までお読みください。
新しい活路を見つける
高校3年生の県大会200m決勝で、2年生の選手に負けた為末選手はとてつもなく大きな挫折を味わうことになったそうです。
これまで、走ることに関しては負けたことがなかった選手が年下の選手に負けたのですから、その時のショックはさぞ大きかったことでしょう。
トラックで負けることは、自分の全人格を否定されることのように思えたのです。
pp10-11
私は追い詰められ、そして、ついにその日がやって来ました。
高校3年生のときです。県大会の200m決勝で、2年生の選手に私は負けました。走ることで初めて負けたのです。
その後、400mで世界ジュニア選手権に出場した為末選手は、再度大きな挫折にぶつかります。
私がフラットレースからハードルへ転向したのは、高校3年のときでした。
pp93-94
20歳未満の選手が出場する世界ジュニア選手権の代表に選ばれ、400mのフラットレースに出場した私は、ジュニア日本新記録となる46秒03で走ったのですが、順位は4位で、トップでゴールした選手とは10mも差がありました。
しかも、そのトップだった米国人選手に話を聞くと、アメフトとの掛け持ちだというではありませんか。そして、その後、結局、彼は陸上をやめてアメフトでプロになるのです。
私は、自分と世界との差に愕然としました。
しかし、そこで陸上競技のすべてを諦めなかったのが為末選手のすごいところです。
為末選手が400ハードルへの転向を決意した顛末が以下のように語られています。
うちのめされたまま競技場に残った私は、ちょうど行われていたハードル競技を見ていました。しばらく眺めているうちにしぼんでいた体がある直感で満たされ始めるのを感じたのです。
p95
それは、
「ハードルでなら、世界で勝負できるかもしれないぞ」
という直感でした。
ハードルは日本人向き
そういう直感を持ったのは、背が高く足の長い外国人選手が、かえってその体を持て余し、とても窮屈そうにハードルを飛んでいたからです。ハードル間の歩数も一定していないようで、踏み切りを合わせるのにも苦労していました。
これだけロスのある走り方をしているなら、こちらがロスなくスムーズに走れば何とか勝負していけるのではないか、と感じたのです。
自分が得意だと信じていることで挫折を味わったとき、私たちは全てを投げ出してしまいがちです。
しかし、為末選手のように同じジャンル、似たようなジャンル、関連性の高い分野で新しい活路を見出すことはできるのです。
実は、私たちが仕事にしていることの多くは「走る」スキルよりも応用がはるかに効きます。
一つのプロジェクトで失敗してしまった、一つの企業でなかなか成果が出ない、そんな時に周りを見回してみたらチャンスは自分が考えている以上にたくさんあることに気がつくことでしょう。
または、新しい「種目」を作ってしまえばいいのです。
陸上競技では新しい種目を作ることは難しいかもしれませんが、仕事であれば新しい仕事を作ったり、新しいプロジェクトを立ち上げることは比較的簡単です。
スポーツであっても、足が早ければ、陸上にこだわる必要はなく、ラグビーでもサッカーでも足の速さを行かせるスポーツはたくさんあるのです。
もうダメだと感じたならば周りを見渡してみましょう。
他の道は常に用意されているのです。
成功する方法を徹底的に考える
為末選手が他の選手と大きく違うところは、自分自身でどうしたら自分の足が速くなるのかを徹底的に考え抜いて、研究したところでしょう。
その結果、為末選手は外国人選手と日本人選手ではそもそも体の構造が違うので、足の速い外国人選手のトレーニング方法を真似ても成果は出ないと言うことに気がつきます。
日本人の体の構造にあったトレーニングを研究を積み課せねながら作りあげていきます。
また、彼はコーチをつけないという決断をしています。
通常の選手であれば、コーチがつき、ほぼコーチの言いなり、またはコーチの考え方と自分の考え方を擦り合わせながら、トレーニングを行なっていくことでしょう。
コーチをつけない理由について為末選手はこのように語っています。
どんなに優れた指導者に恵まれたとしても、自分の思いとのギャップは必ず出てくるでしょう。そういう部分で迷ったり葛藤したりでムダなエネルギーを使うくらいなら、あらゆるリスクを自分で引き受けて、自分の思い通りにやったほうが気持ちが集中できますし、覚悟が固まります。
p108
自分には何が足りないのか。それを解決するためには、何をすればいいのか。
pp108-109
それを自分の脳で突き止めた上で行うトレーニングは、上から降りてきたメニューをこなしている場合とは、効力が雲泥の差になるのです。
責任は全て自分で背負ういう覚悟と、自分自身で考えて意識をするからこそ、上達すると彼は述べています。
仕事も同じではないでしょうか?
最初は上司からの指示に忠実に仕事をこなしていきます。
そのうち、上司の意見と自分の意見に齟齬が生じることがあります。
それで成果が出なければ、全て上司の責任する。
しかし、いざ自分でやってみても成功はしない。
だから、そこで何度も失敗をして試行錯誤をして、技術や知識をその過程で自分のものにしていく必要があるのです。
自分で考えて自分で行動をする。
為末選手の強さは自分自身で徹底的に考え抜いて、それを自分の責任のもとで実行してきたと言うことにあるのではないでしょうか。
自分が目指すべきレベルにいる人たちと時間と体験を共有する
世界の強豪と戦うためには、常に世界の強豪たちと勝負をしなければならないと考えた為末選手は、大学卒業後に就職した大阪ガスを1年程度で退職します。
企業に勤めて午前中だけ仕事をして、午後は練習に専念する。
怪我をしても、引退しても、その後は会社が面倒をみてくれる、と言う恵まれた環境。
そのような環境が日本人を勝てなくしていると為末選手は考え、どこにも所属をしないプロ選手として世界の大会を巡りはじめます。
その際には、周りには大反対をされたそうです。
しかし、為末選手の考え方は次のとおりです。
世間のアドバイスというのは、「こうしたほうが安全なことが多い」という統計的な経験知によるものだと思います。それはそれで大切なことですし、少なくとも周りの人が善意でそれを言ってくれることもわかっています。
p91
けれども、私たちアスリートは、失敗した時のことをあらかじめ計算する暇があったら、どうすれば自分の潜在能力を最大限に爆発させられるかを最優先して考えるべきなのです。
まず踏み出してみること。それが大切だと私は思います。考えすぎずに、まず動いて、ある意味、流れに身を任せてみることです。
そこで、世界の強豪たちと常に勝負をすることで、人間として強豪選手を見ることができ、そこに余裕が育ってきたといいます。
最初のうちは周りの選手全員が自分より早そうに見えましたが、実際に一緒に走ってみて、そんなことはない、とわかってしまえば、なんということはありません。
p89
相手も同じ人間なのです。自分より速い選手もいれば遅い選手もいる。アフリカ系選手であろうが欧米系選手であろうが、緊張のあまり震えることもあれば、レースに負けて泣いていることもあります。
このような経験から生まれた気持ちの余裕が2つ目のメダルに繋がったと為末選手は述べています。
二つ目のメダルを獲得したヘルシンキ大会。
大雨で決勝の時間が大きくずれ込み、イライラ、ソワソワする選手が多い中為末選手は寝そべっていたと言うのです。
その気持ちの余裕が明らかにメダル獲得につながり、彼の努力、信念が身を結んだ瞬間だったと言えるでしょう。
私たちも、適度に仕事をして、それに見合ったお給料をもらったいれば、その状況に甘んじてしまうことがほとんです。
しかし、それ以上の成長はありません。
今、以上に成長したければ、自分の目指す場所で活躍している人々と時間や体験を共有することです。
それを為末選手は大阪ガスを退職してやってきたことなのです。
より高いレベルに行くために、よりレベルの高い場所に身を置いてみることをお勧めします。
勝たなければいけない勝負のために負けることを許す
為末選手は自分のことを「一発屋」といいます。
ただし、一発では終わらない一発屋といいます。
その心は、常に勝ち続けることは自分にはできないので、勝たなければいけない試合だけに勝てるように、他の試合での負けを許し、狙った勝負に最大限の力を注ぐと言うのです。
アテネははっきりと教えてくれました。それは、私がまぎれもない「一発屋」である、ということです。少なくとも、五輪や世界陸上といった大一番で結果を出したければ、一発屋に徹するべきだ、ということです。
p161
高いレベルでアベレージを維持して目標に臨むのではなく、あえて大きな波を作り反動を利用し助走をつけて、最大限の力を狙ったレースにたたきつけなければ勝負にならないのです。
私は一発屋です。
ただし、一発では終わらない一発屋なのです。
常に高いレベルで勝ち続けると、さすがに身も心もボロボロに疲れ果ててしまいます。
世界の強豪にはそれを可能にしている選手もいるのでしょうが、為末選手は自分自身はそんな選手ではないと自覚をしているのです。
スポーツ選手といえば、常に勝つか負けるかの勝負をしなければいけないかのように思われますが、そうではなくて、どうしても勝たなければいけない試合に勝つために、負けてもいい試合には負けてもいいというのです。
とりわけ、自分に適したピーキングの方法をつかんだことは、一発屋の自分にとってかけがえのない財産でしょう。虚栄心を捨て、負けていい勝負を負けられるようになったのは、プロの陸上選手として大きな成長だと思います。
p170
わたしたちの普段の仕事でもそうかもしれません。
できる人は意外と手を抜けるところで手を抜いていたり、他の人に仕事を振り分けたりしています。
しかし、重要なプレゼンテーションがある時は、徹夜をすることもあれば、身なりを気にせずにその仕事に注力したりします。
そもそも人間には全てを完璧にこなすことはできないのです。
全てを完璧にしようと思うからこそ、逆に重要な場面でミスをしてしまうのです。
力を抜けるところは力を抜いて、全力を尽くさなければいけないところで、全力を尽くす。
そういう生き方、考え方が為末選手を強くしているのでしょう。
まとめ
日本の陸上競技史上、トラックの個人種目で2つのメダルを獲得している選手は為末選手だけです。
そもそも「足が速かった」という天才ではありましたが、それだけではなく、それにプラスアルファされた、彼の努力と考えに考え抜いた、自分の足を速くするトレーニングの結果が2つのメダルにつながっているのです。
天才であっても、何も考えずに、流れに任せて勝負をしていたのでは結果はともないません。
多くの天才が、結果を残すことができずに消えてしまっているのも事実です。
為末選手の強さの秘密は、以下の4点にあると思いました。
- 常に勝つために新しい活路を見いだす努力をする
- 成功する方法を徹底的に自分自身で考え抜く
- 自分が目指すべきレベルにいる人たちと時間と体験を共有する
- 勝たなければいけない勝負のために負けることを許す
そして、これら4つの秘密は、わたしたちのような普通の人たちが実践すべきことでもあります。
これら4つを実践することで、明らかにあなたの人生は好転することでしょう。
ぜひ、一度、考えてみてください。
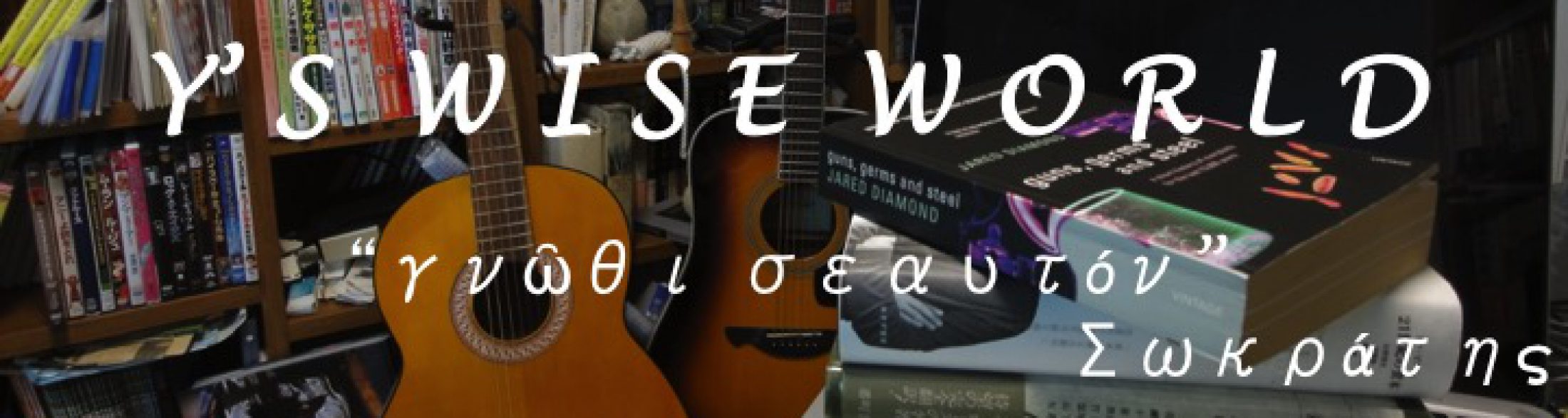


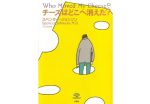





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません